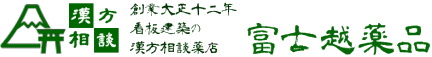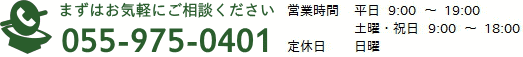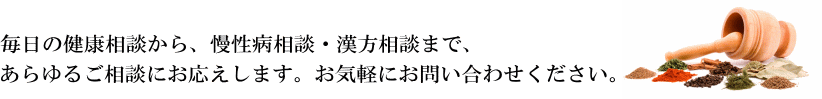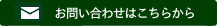ページ内目次
女性、こどもの保健
・ 女性の保健
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
|
冷え・のぼせ・便秘 |
桃核承気湯 |
のぼせて足・腰が冷え、便秘がち。左下腹部に圧痛を認める方の月経困難、腰痛に。 |
|
おりもの・尿のにごり |
竜胆瀉肝湯 |
おりもので下着の汚れが気になる方に。また下半身の炎症による陰部のかゆみに。 |
|
冷え・のぼせ・肩こり |
桂枝茯苓丸 |
産後のおりもの、出産後の体力低下に伴う発熱・頭痛・めまい・イライラ・動悸に。また育児ノイローゼに。 |
|
産後の諸症状 |
きゅう帰調血飲第一加減 |
のぼせて足冷えを訴えるなど血液の循環が悪い方の肩こり、下腹部痛、月経不順に用いる。 |
|
月経痛 |
折衝飲 |
月経時に痛みが強くて気分がすぐれない方に。また痛みが激しく鎮痛剤を必要とする方に。 |
|
イライラ・気疲れ |
加味逍遙散 |
気疲れ・気苦労が多く、イライラして肩こり、頭痛など多彩な症状を訴える自律神経失調症・更年期障害に。 |
|
貧血・冷え症 |
当帰芍薬散 |
体力がなく、貧血で疲れやすく、ナツでもからだが冷えやすい方に。月経不順・産前産後の保健にも。 |
・ こどもの保健
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
|
呼吸器型 |
小柴胡湯 |
呼吸器が弱く、かぜをひきやすく、なかなか治らない方に。食欲不振と疲労感のある小児の体質改善にも。 |
|
神経質型 |
柴胡清肝湯 |
かんの強い小児の扁桃炎、湿疹、夜なきなどの神経症に。小児の体質改善、アトピー性皮膚炎に。 |
|
胃腸虚弱型 |
小建中湯 |
体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動悸、手足のほてり、冷え、頻尿および多尿などを伴うこどもに。 |
|
疲労型 |
六味丸 |
疲れやすく、尿量減少または逆に多尿で、ときに口の渇きを訴える夜尿症に。 |
冷え性は女性に多い
冷え性は、体の一部、たとえば足や手先、腰や膝などが冷えてとくに冷たく感じる症状で、ひどい人は夏でも靴下をはいて、厚着をせざるを得ないというものです。西洋医学的に見ると、これは冷感部位の毛細血管が収縮して血行がうまくいかないためですが、その原因としては、ホルモンのアンバランス、自律神経機能のアンバランスから血管運動の神経が障害されるためといわれています。
冷え性の養生
①質的にバランスのとれた食事をすること、タンパク質は充分に取るようにし、青野菜などは煮て食べること、小魚、豆腐を多くとることです。また、妊婦や高齢者は特にカルシウムが不足しがちです。
②イライラや取り越し苦労は禁物です。
③睡眠を充分にとり、手、足、腰などの保温に気をつけ、適度な運動をするようにしましょう。
④冷え性の方は水分の摂取がどうしても多くなりがちのようです。くだもの、ジュース、その他の水分の多いものはひかえめにしましょう。
⑤他の病気のある人は、それぞれの病気に対する養生をよく守って下さい。
ミドル、シルバーの保健
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
|
肥満型 |
防風痛聖散 |
脂肪太り体質で、腹を中心に脂肪がつき、便秘する方。高血圧に伴う肩こり・のぼせ・動悸に。 |
|
肩こり・便秘型 |
大柴胡湯 |
がっしりとした体格で、便秘しやすく、みぞおちが硬く張って痛い方。高血圧に伴う肩こり・頭痛に。 |
|
頭痛型 |
釣藤散 |
朝起きがけにいつも頭痛があり、肩こりや目の充血がある。頭痛により気分がうっとうしい、さらに物忘れがひどい方に。 |
胃腸虚弱型 |
補中益気湯 |
胃腸虚弱で食欲がなく、手足がだるく、身体が疲れやすい。病後の衰弱、ねあせ、夏バテなどに。 |
口渇・頻尿型 |
八味丸 |
特に腰から下が疲れやすくて、脚腰が痛み、お小水が近く、口が渇いたり、目がかすんだりする方。また勢力減退にも。 |
むくみ・腰痛型 |
牛車腎気丸 |
八味丸の作用をさらに増強したもの。下半身がむくんだり、膝がガクガクする方に有効。 |
過労型 |
知柏地黄丸 |
手足のほてり、顔ののぼせ、口渇など熱感が顕著な方。 |
疲れ目・かすみ目型 |
杞菊地黄丸 |
目がかすむ、まぶしい、目が痛い・疲れるなど目の症状に特によい。 |
疲労感 |
十全大補湯 |
もっとも体力が低下した時に用いられる代表的な漢方薬。病後の体力低下、慢性的な疲労または貧血、食欲不振、ねあせに。 |
生涯盛年
我が国の平均寿命は世界一となり、2020年には4人にひとりが高齢者になるといわれています。即ち健康で生活できる期間が長くなったといえます。 しかし高齢になるにしたがって、病気になっても回復が遅い、慢性化しやすい、いくつかの病気をかかえるなど身体の衰えが現れてきます。老化を遅らすにはバランスのとれた食事、適度な運動を心掛け、そして、自分のことは自分でやるといった積極的な生活態度が必要です。体力の低下のほか局所に老化の現象がでてきますので注意して下さい。
肥満
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
脂肪太り型 |
防風痛聖散 |
脂肪太りで腹が突き出たタイプでよく便秘する。また動悸、肩こり、のぼせなどを訴える方。 |
堅太り型 |
大柴胡湯 |
肥満傾向で体格がガッシリし、便秘がち。みぞおちが硬く張り、肩がこったり、頭痛を訴える方。 |
|
水太り型 |
防己黄耆湯 |
水太りで、汗をかきやすく、すぐ疲れる。またからだや関節がむくんだり、関節痛を訴えることがある方。 |
健康的にやせるための7つのポイント
①減量の目的と目標をはっきりさせる
普通は20代の最も調子が良かった時が理想体重です。
②減量は長期的に
無理をして短期間に大幅に減量しても、すぐ元の体重にもどってしまいます。1ヶ月2~3kg程度の減量が限度です。
③バランスのよい食事を心掛ける
摂取カロリーは男性1,500kcal、女性1,200kcal程度が適当。朝食は量多く、夕食は軽く、ゆっくりと食べること。間食、甘味食品、アルコールは禁止し、デンプン質を制限して下さい。
④自分に合った運動を生活に
1日200kcal程消費できるような運動を心掛けて下さい。激しい運動よりも心拍数が120~140程度になる中程度の運動が効果的です。
⑤ストレスや不満を解消する
ストレスや欲求不満を食行動にぶつけていませんか。情緒の安定-それが減量につながります。
⑥途中で挫折せず根気よく続ける
減量中の体重の停滞期間は、この後の大幅な体重減少の信号です。がんばってその時期を乗り切って下さい。
⑦自分に適した漢方薬を服用する
太り過ぎに多い体質的なかたより(食毒体質や水毒体質)や症状によって漢方薬を選びます。
咳・喘息
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
コンコン型 |
麻杏甘石湯 |
咳が激しく、ほとんど痰が出ないもので、咳き込むとノドが渇き、頭部がびっしょり汗をかく方。 |
ゼイゼイ型 |
小青竜湯 |
うすい水様の痰を伴いゼイゼイと咳き込む気管支喘息や気管支炎に。 |
|
混合型 |
小青竜湯合麻杏甘石湯 |
咳が激しく、発作時に頭部に汗をかき、呼吸困難を伴い、のどが乾く方。 |
胃腸虚弱型 |
参蘇飲 |
胃腸虚弱で、かぜや気管支炎により、激しい咳ではないが、いつまでも咳が長引く方。 |
ゴホンゴホン型 |
麦門冬湯 |
のどが乾燥して痰が切れにくく、こみ上げてくるような強い咳をして赤くなる方。 |
気管支喘息の養生
気管支喘息は、アレルギーに起因するものが多く、例えば、ほこり、花粉を吸ったり、カニ、エビ、鶏卵、牛肉、魚などを食べたりした場合に発作が起きることがあります。しかし、単なる食事制限ばかりに気をとられていてもこの病気はよくなりません。また小児喘息では、母親が過保護であったり、両親が共に働いていて子供に接する機会が少ないことが大きな要因になっていると言われています。
①規則正しい生活を送り生活にリズムをもつこと
過労をさけ、充分休養をとる。カゼをひかないように心掛ける。
②食べ物、飲み物、嗜好品
アルコール、タバコ、コショウなどの刺激物はさける。ジュース、コーラ、ビール、みかんなど水分の過剰摂取はさける。
③その他、暴飲暴食はしない
④適度の運動をすること
⑤乾布摩擦や日光浴などもよい
⑥精神の安定
イライラしたり、激怒するようなことをさけ、心静かな生活を送ることも大切です。
感冒(かぜ)
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
|
葛根湯 |
かぜの初期の代表薬。比較的体力のある方で発熱・悪寒が強く、肩や首筋がこる方 |
夏カゼ型 |
霍香正気散 |
からだが熱くほてって、頭痛・発熱し、冷飲食のため、嘔吐・下痢などの胃腸障害を起こす。暑気あたりにも。 |
|
|
小青竜湯 |
くしゃみ、鼻水、咳や痰などを訴えるかぜに。 |
|
胃腸虚弱型 |
参蘇飲 |
胃腸虚弱で、かぜが治ったがいつまでも咳が残る。 |
|
微熱型 |
柴胡桂枝湯 |
自然に汗ばんで、微熱、寒気、吐き気などを伴う。 |
|
気うつ型 |
香蘇散 |
胃腸が弱く、頭痛がして、気分がすぐれないといったかぜの初期に。 |
感冒の養生
①安静、保温、栄養の三原則
安静は多くの病気の治療でもっとも根本的なもので、かぜの場合も病気の治り方をはやめ、また肺炎などの合併症を防ぐ意味があります。かぜでは「第1日目の安静」と言われますが、かぜのひきはじめの時期に充分に安静をとると、急速に回復することが多いからです。ことに熱のある間や、咳が激しい時は、できるかぎり仕事や家事を休み、床につくことです。 第二に大切なのは保温です。部屋を暖かくし、時々窓をあけて換気をして、寝具にも充分注意します。また入浴はよくないが「衣浴」と言って、入浴にかわるぐらい皮膚の清潔は重要なので、肌着を取り替えることは大切です。汗をかいたのに下着をかえないでおくと、汗が蒸発するときに身体からの多量の熱をうばい、そのため身体が冷え過ぎ、かぜ事態にかえってよくないのです。
②かぜのときの食べ物
次は栄養を充分に摂ることが大切です。特にタンパク質やビタミンは、ストックがきかず、毎日一定量をとる必要があり、また病気になると、これらは余計必要となります。したがって、カサが少なくて消化がよく、しかも栄養価の高いものが良いわけです。またビタミンB1の豊富な、たらこ、豆類などをすすんで摂るべきです。生の冷たいもの、肉類や消化の悪いもの、刺激物を禁じます。小青竜湯の人、すなわちくしゃみ、鼻水、水っぽい痰の多い人は、水分過剰ですから水気の多いものを禁じます。
③かぜの予防
病原体が少しぐらい侵入してきても、それに打ち勝つだけの強い抵抗力を保っておくことが第一です。普段から扁桃腺をよく腫らす人や呼吸器の弱い人は、体質改善が必要です。体質に応じて、柴胡桂枝湯、小柴胡湯などを服用します。また寒さに対する訓練、乾布摩擦、冷水まさつ、薄着などは更によいでしょう。
鼻の病気と症状
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
炎症型 |
辛夷清肺湯 |
膿性の鼻汁が出たり、あるいは鼻腔内が乾燥し、熱感があり、かゆみ、痛み、鼻づまり症状の強いちくのう症、慢性鼻炎に用いる。 |
鼻閉型 |
葛根湯加辛夷川きゅう |
鼻づまりが激しく、頭が重く、肩がこり、気分がイライラして落ちつかない方。ちくのう症では膿性の鼻汁を伴う。 |
|
鼻汁型 |
小青竜湯 |
くしゃみを連発し、鼻水が多く、時には鼻づまりを伴う方。花粉症などに。 |
体質改善型 |
荊芥連翹湯 |
ちくのう症やアレルギーによる鼻炎がなかなか治らず、また鼻炎はあまり強くないが、よく繰り返す方。 |
アレルギーの養生
①生活環境と生活態度の改善が大切
(ⅰ)生活環境-室内や身のまわりを清潔にしてホコリをたてない。部屋の換気は温度調節に留意する。日当たりを良くしてカビや湿気を防ぐ、などが大切です。
(ⅱ)生活態度-感冒や疲労は、身体の抵抗力を弱め自律神経のバランスをくずし、いろいろな病気のもとになります。精神的、身体的な安静をはかり、充分な睡眠と栄養と取ることが重要です。
②冷えは大敵 冷えは血液循環を悪くし、いろいろな症状を引き起こします。鼻アレルギーの場合にも抗原との接触も無しに鼻アレルギーの症状を発生させたり、悪化させたりします。「頭痛足熱(ズカンソクネツ)」というように上半身を涼しく、下半身を温かくする事が身体の正常なリズムを維持するうえで大切な基本です。
(ⅰ)家庭温泉-片手に二握り程の塩か重曹を入れて、おへそが隠れる程度に身体を入れると、下半身がよく温まります。また身体を芯から温める酵素・生薬配合入浴剤もあります。
(ⅱ)肩こう骨の間をよく摩擦する-小青竜湯の適応する人は肩こう骨の間あたりが冷たいと感じる事があります。この周りを乾いたタオルで赤くなるまでこすると身体が温まります。
③「水毒」を悪化させる食物を控える
水分を摂りすぎたり、身体を冷やす物を多く摂りますと、「水毒」をいっそう悪化させます。ビールや清涼飲料水をはじめ、果物類も余り摂り過ぎないように注意して下さい。反対に根菜類は温める働きがあると言われています。特に煮た物が良いようです。
皮膚の病気と症状
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
|
|
化膿 |
辛夷清肺湯 |
膿性の鼻汁が出たり、あるいは鼻腔内が乾燥し、熱感があり、かゆみ、痛み、鼻づまり症状の強いちくのう症、慢性鼻炎に用いる。 |
|
カサカサ・カユミ型 |
当帰飲子 |
かゆみが強いが、炎症や分泌物が少なく、皮膚がカサカサして、手足のひえを伴うことがある。老人の皮膚掻痒症に。 |
|
カユミ型 |
消風散 |
熱感が激しく、かゆみが強い湿疹。患部は汚く、分泌物が多いが逆に乾燥することもある。夏に悪化しやすい傾向のある慢性湿疹に。 |
|
アトピー型 |
柴胡清肝湯 |
神経質で手足の裏に汗をかきやすく、皮膚が浅黒い方の湿疹に。患部は乾燥して、かゆく、熱をもつこともある。小児のアトピー性皮膚炎にも。 |
|
|
若年型 |
清上防風湯 |
身体の丈夫な方で、顔がのぼせやすく、赤くて大きなニキビに。比較的若い人に多い。 |
|
月経不順型 |
桂枝茯苓丸加ヨクイニン |
のぼせ症で手足が冷え、女性では月経異常や月経痛のあることが多い方のニキビ、シミ、主婦湿疹に。 |
|
体質改善型 |
荊芥連翹湯 |
皮膚が浅黒く、手足の裏に汗をかきやすく、化膿しやすい体質。体質的にニキビのできやすい人に用いる。 |
|
|
シミ型 |
加味逍遙散 |
貧血ぎみで血色が悪く、皮膚がカサカサに荒れやすく、イライラして精神不安を伴う方のシミに。 |
|
|
シモヤケ型 |
当帰四逆加呉茱萸生姜湯 |
しもやけをはじめ、冷えからくる頭痛・腰痛・下腹部痛に用いる。 |
肌あれ型 |
ヨクイニン |
はとむぎの種子からエキスをとり錠剤にしたもの。イボ、カサカサして肌が荒れる方に。 |
皮膚病の養生
ニキビ、湿疹、ジンマ疹をはじめとする皮膚疾患は、個人の体質、症状によって養生も変えなければなりませんが、ここでは一般的な養生の原則を述べます。
①偏食を正すこと
子供に多いアトピー性の湿疹などは、偏食を正すことによってずいぶんと改善されます。ことに、牛乳、チーズ、肉、卵、魚といった動物性タンパク質の摂取過多と野菜不足の改善を。
②炎症を増長する刺激物をひかえること
患部が充血し熱感、カユミを伴うものは炎症があるので、酒類、コーヒー、香辛料、豚肉など脂肪の多い食品、チョコレート、ようかんなど糖分の多い食品を控えましょう。ジンマ疹はカニ、サバ、エビ等がアレルゲンの人があります。
③外から患部を刺激しないこと
カユミを伴うものが多いですが、かけばかくほど炎症はひどくなり、ひっかき傷を作って悪化させることになります。軟膏でカユミをおさえることも大切です。また患部を清潔にするため、石けん、化粧品、シャンプーなどにも気をつけましょう。
④新陳代謝をよくし解毒をはかること
排便、排尿、発汗などの生理作用が悪くなると、体内の毒素の排出がうまくいかず、これが皮膚病にも悪影響を与えます。便通をよくし、汗をかいて入浴シャワーで清潔にするのも大切です。
⑤精神的緊張、ストレス
精神的な緊張や不安感が症状を悪化させる原因になることが少なくありません。精神的ストレスをさけ、笑顔を作るようにし、充分な睡眠をとり、疲労を回復しましょう。
泌尿器の病気と症状
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
炎症型 |
猪苓湯 |
尿量が減少し、排尿痛、残尿感のある腎臓・膀胱の疾患に。また下半身のむくみ、血尿などにも効果がある。 |
反復型 |
五淋散 |
頻尿、排尿痛、残尿感を訴える尿道・膀胱炎に。またこのタイプの方は炎症が明らかで、痛みも激しい。細菌感染によって、膀胱炎を繰り返す方にもよい。 |
|
浮腫型 |
五苓散料 |
のどが渇いて、尿量が減少し、むくむ方に。嘔吐、頭痛などにも。 |
|
ほてり・排尿困難型 |
六味丸 |
疲れやすく、口が渇き、手足がほてり、水分をとるにもかかわらず尿量減少する。排尿困難、むくみに。 |
|
頻尿型 |
八味丸 |
疲れやすく、尿量が減少または逆に増大することがあり、口渇くを訴える。手足が冷えたり、ほてったりする。 |
|
排尿困難型 |
牛車腎気丸 |
八味丸の作用をさらに増強したもの。下半身がむくんだり、腰が痛んだり、膝がガクガクする方に。 |
腎臓病の養生
腎臓はそら豆状の左右一対の臓器で、ここで尿を作り膀胱へ尿を送っている臓器です。また、大人の排尿回数は1日5回くらいが平均で、排尿量は1500mlくらいが正常値とされています。
漢方では、水滞または水毒の病気といわれるように、体内の水分の調節あるいは代謝をよくすることが養生法の一つのポイントといえます。
①水分・食塩・タンパク質が基本
(ⅰ)急性の時は尿量が少ないため水分の多量摂取が西洋医学の原則ですが、ミカン、ナシ、バナナ、ジュースなどのように体内を冷やすものは避ける。
(ⅱ)食塩はムクミや血圧が高い時に制限が必要。
(ⅲ)タンパク質は血中に尿素がたまった状態で尿量が少ない時に制限が必要です。ネフローゼにはむしろ、大量のタンパク食が必要です。
食塩とタンパクの制限に神経質になりすぎは、かえって病状を悪くする可能性があります。
②腎臓病によい食品
黒豆、小豆、モヤシ、ゴボウ、コンニャク、ジジミ、人参、レンコン、ナマコ、そら豆、玄米の胚芽、銀杏、トウモロコシ、小魚類、また魚肉類は全て煮た物を食べた方がよく、卵は卵黄だけの方がよいとされています。
③その他注意すべき点
(ⅰ)冷え性や体力の弱い方は、体力、抵抗力を養うこと。
(ⅱ)カゼをひかないようにすること。
(ⅲ)酒、刺激性のある飲食物、砂糖、油類などのとりすぎに注意。
(ⅳ)暴飲、暴食をして胃腸をいためないこと。
(ⅴ)腎臓は冷えに敏感な臓器ですので、冷たい食物のとりすぎや、冷房などにより身体を冷やしすぎないように気をつけて下さい。
胃腸の病気と症状
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
胸のつかえ・便秘型 |
大柴胡湯 |
体力があり、食欲も旺盛であるが、食べると胸脇部がつかえ、ときにはきけを訴え、便秘をする方。 |
痛み型 |
四逆散 |
ストレスにより胸脇部がつかえるが、便秘はない。腹痛を伴う神経性胃炎、胆のうの病気などに。 |
|
疲労・はきけ型 |
小柴胡湯 |
はきけ、むかつきがあり、食欲もあまりなく、胸脇部がつかえて、疲れやすい方。 |
胃痛型 |
安中散 |
やせ型、神経質な方で、食後胃がもたれて痛み、胸やけ、ゲプを訴える方。ストレスからくる胃痛、腹痛にも。 |
腹痛・食欲不振型 |
柴胡桂枝湯 |
食欲がなく、胸がつかえ、だるさを訴え、腹痛、胃痛が顕著である方。 |
下痢・何便型 |
六君子湯 |
胃腸虚弱でみぞおちがつかえ、冷えにより激しい腹痛、下痢を起こし、食欲がなく、疲れやすい方。 |
下痢・腹鳴型 |
半夏瀉心湯 |
みぞおちがつかえて、腹がゴロゴロ鳴り下痢をして、食欲不振ではきけ、ゲップを伴う方。 |
冷え性型 |
人参湯 |
胃腸虚弱でみぞおちがつかえ、冷えにより激しい腹痛、下痢を起こし、食欲がなく、疲れやすい方。 |
痔型 |
乙字湯 |
便が硬くて便秘しやすい方の、いぼ痔やきれ痔に。また便秘により悪化するものに。 |
便秘型 |
麻子仁丸 |
病後や老人の方で体液が不足し、便が固めの常習便秘の方。 |
気をつけたい食事
①飲食物の質と量
飲食物は量を少なく、消化しやすい、栄養価の高い、バラエティに富んだものが理想的です。
米麦の問題・・・米麦はよくないと言われますが、こだわる必要はありません。米食では玄米あるいは五分づきをメン類も多食はしない方がよい。
脂質、糖質、タンパク質・・・いずれにも片寄るのはあまりよくありません。
酒、タバコ、コーヒー、香辛料・・・いずれも胃腸の粘膜を刺激したり神経興奮をもたらし、よくありませんが、ケースバイケースで適量が必要なこともあります。
野菜と果物・・・一般によいが、野菜はなるべく煮たきすること、果物は胃腸を冷やすカキ、ミカン、ナシ類は体質によっては制限が必要なこともあります。
水もの・・・漢方では水毒を重視します。水ものを摂りすぎて胃腸に負担をかけすぎないよう注意する。
熱いもの・冷たいもの・・・極端に熱いものや冷たいものを多量に摂らない。
②食事の仕方
回数と時間・・・回数は3回でなくてもよく、毎日決まった時間に規則正しく、なるべく少量を何回かに分けて食べるのがよい。
食後の安静・・・食事の直後は休息をとるのがよく、急激な運動や労働はよくありません。
食事の環境・・・食事中および食後は精神を緊張させたり、心配事、騒音などイライラする環境は避け、楽しく食事すべきです。
高血圧に伴う諸症状
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
筋肉質・過信型 |
大柴胡湯 |
がっしりとした体格で、みぞおちが硬くはって苦しく、便秘をする方。高血圧に伴う肩こり、頭痛。 |
肥満型 |
防風痛聖散 |
脂肪太り体質で、腹を中心に脂肪がつき、便秘をする方。高血圧に伴う肩こり、のぼせ、動悸に。 |
|
精神不安型 |
柴胡加竜骨牡蛎湯 |
比較的体力があるが、精神不安によって高血圧の随伴症状(動悸、不眠、不安)を訴える方。 |
|
頭痛型 |
釣藤散 |
特に起床時または午前中に頭痛・頭重を訴える方。また慢性の頭痛や高血圧に伴う頭痛にも。 |
|
虚弱体質型 |
七物降下湯 |
からだが虚弱で高血圧に伴う頭痛、肩こり、のぼせ、耳鳴りなどを訴える方。 |
|
のぼせ・熱感型 |
黄連解毒湯 |
顔はのぼせて赤く、熱によって気分が落ち着かずイライラする傾向があり、不眠を訴えたり、血圧が上がったりする方。 |
|
動悸・めまい型 |
苓桂朮甘湯 |
不安感があって、動機、めまい、ふらつきのある方や不安感が強いと血圧が変動しやすく、動悸やめまいなどを訴える方。 |
高血圧・動脈硬化も気持ちしだい
高血圧・動脈硬化にはストレスや心理的・社会的因子の関与が往来から認められていました。一方、アメリカのフリードマンとローゼンマンらの「A型行動パターン」の指摘により、動脈硬化との関係が明らかにされました。
A型の行動パターンとは
1、性急でいらつきやすい
2、時間に追いたてられている感じが強い
3、仕事に対する責任感が強い
4、攻撃傾向および競争心が強い
5、語気の激しいしゃべり方をする
などの特徴があり、このような性格を有した人はその正反対の人(B型行動パターン)に比べ、2倍以上の羅患率を示すと報告されています。
日本人についても同様の結果が報告されていますが、欧米のA型行動パターンが攻撃性を核としているのに対し、日本人のそれは仕事中心主義を核としているという違いがあります。
神経痛・腰痛・関節痛
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
肩こり型 |
独活葛根湯 |
普通の肩こりから五十肩(ひどいと腕の上げ下ろしができない、首がまわらない)まで用いる。 |
|
疼痛型 |
慢性型 |
関節・筋肉が腫れて熱をもち痛む方や慢性でやや重症の方に。関節に水がたまって、手足が重だるい方に有効。 |
亜急性型 |
関節や筋肉の炎症、神経痛でからだのあちこちが痛む方。慢性化して症状はあまり激しくないが、夕方になると痛みだし熱がでる。 |
|
|
神経痛型 |
疎経活血湯 |
日頃からお酒をよく飲む方で、夜間など冷えると痛みが増悪する。主に腰から下の神経痛、、関節痛、腰痛などに。 |
|
膝関節炎型 |
防已黄耆湯 |
水太りで皮膚にしまりがなく、汗をよくかく反面、下半身がむくみやすい。膝関節に水がたまり、腫れ、いつも下半身がだるく重い方に。 |
|
腰痛型 |
若年 |
胃腸虚弱で顔色が悪く、上半身がほてり、下腹部・腰・脚など下半身が冷え、そして痛む方。その症状は慢性に経過したもので、あまり激しくない。冷房病にも。 |
実年 |
疲れやすくて、手足が冷え、お小水が近く、ときに口が渇き、下半身に脱力感、痛み、しびれなどを訴える方。 |
|
冷え性型 |
桂枝加朮附湯 |
冷え性で、手足の関節や筋肉が腫れて痛み、屈伸が困難な方。尿量は減少して、冷えると増悪し、麻痺感がある。 |
打撲型 |
治打撲一方 |
打撲によって起きた腫れや痛みに。捻挫、外傷による内出血にも。 |
神経痛・腰痛・関節痛の養生
神経痛、リウマチの原因は、内的要因と外的要因の二つがあり、内的要因は患者さんの体質的特徴と生活内容(食事・心身の疲労)などであり、外的要因は、冷えと湿気、気候、生活環境などです。西洋医学ではとくにリウマチに対しては「一般的基礎法」といって、一 運動、二 安静、三 栄養、四 保温、五 感染除去などを重視しています。
①冷え込みと湿気を避ける
身体の内的要因として、西洋医学では、アレルギー体質とか関節、神経組織の過敏体質、遺伝とか年齢、またはリウマチは女性に多く、男性に少ない(3対1)ともいわれます。漢方では「水毒」、「お血」という体質的要因を重視して薬をすすめるとともに、外的要因として風(冷え込み)湿(水毒)を重視し、食養、養生、手当もこの原則に従います。身体を湿らさないこと。衣服、夜具などの乾燥、保温、水仕事などで冷たいところに長時間いないこと、マッサージをよくすることが肝要です。
②利尿、便通、入浴、マッサージ
水毒体質のものは、上述の冷え込み、湿気はもちろん、食べ物についても冷たいもの、水分の多いもの(ナシ、ミカンなどの果物を含む)、砂糖類はなるべく避けること、マッサージ、入浴などによって発汗をはかることが大切です。
③その他
お血体質で、冷えのぼせ、便秘の方は動物性タンパク質、脂肪を多く摂ることはよくありません。酒、タバコ、その他刺激性の飲食物もよくありません。ただ冷え症で、貧血症の方は、水毒体質を兼ねる方も多く、同じようなものをひかえます。便秘は、神経痛にもリウマチにも大敵ですので、便通を毎日つけるように工夫しましょう。また心の持ち方も大切で、正しい知識をもち、あせらず楽しく過ごすことです。
神経症・不眠
|
タ イ プ |
漢 方 薬 名 |
適 応 |
不安・ドキドキ型 |
柴胡加竜骨牡蛎湯 |
脂肪太りで腹が突き出たタイプでよく便秘する。また動悸、肩こり、のぼせなどを訴える方。 |
体力低下型 |
きゅう帰調血飲第一加減 |
冷え性で体力がなく、頭痛、めまい、イライラ、のぼせなどを訴える血の道症、育児ノイローゼに。 |
|
胃痛・腹痛型 |
四逆散 |
ストレスにより胃腸機能が亢進したり、自律神経が失調する方。胸腹部が重くるしく、腹痛を伴う神経性胃炎、胆のう炎に。 |
|
クヨクヨ・心配型 |
半夏厚朴湯 |
気分が沈みがちで、のどから、胸元にかけてふさがる感じがして、動悸、めまい、はきけを訴える方。 |
|
寝汗・微熱型 |
柴胡桂枝乾姜湯 |
神経質で気疲れしやすく、不眠・動悸・息切れを訴える方に。微熱がとれないかぜ・こじれたかぜにも。 |
|
気疲れ・気苦労型 |
加味逍遙散 |
上半身が急に熱くなって汗が出て、その後急に寒くなる。のぼせやすく、ささいなことが気にかかり、イライラして不安定愁訴が多い方。 |
|
緊張・イライラ型 |
抑肝散加陳皮半夏 |
神経が高ぶり、イライラして、怒りっぽい方。興奮のために眠れない人や子供ではひきつけ、チック、夜泣きにも。 |
|
不眠型 |
柏子養心丸 |
肉体的な極度の疲労や神経疲労で眠れない方に。夜中に目が覚める、朝早くから目が覚めて再び寝つかれない方にも。 |
|
のぼせ・不眠型 |
黄連解毒湯 |
のどが渇き、顔はのぼせて赤く、全身に冷えは感じない。イライラして落ち着きがない方の不眠症に。 |
|
不安感・ふらつき型 |
苓桂朮甘湯 |
不安感があって、動機、めまいを訴える方に。急に立ち上がるとふらついたり、めまいしたりする。 |
ぐっすり眠るために
人間の睡眠は、身体のリズムに関係があります。人間の身体のリズムは、昼高くて夜低くなり、活動の低い夜眠るというのは大変効率的です。だから、早寝早起きなど、規則正しい生活をして、決まった時間に眠るようにすることが大事です。その時刻になると、身体のリズムが睡眠に適した状態になるようにしておくのです。
①就寝前に気分転換をする
身体の状態を睡眠に入りやすくするために、気分転換をして日中の活動による緊張をほぐすことが必要です。ジョギング、入浴、あるいは夕食時の団らんもよいでしょう。ただし度が過ぎないように気をつけましょう。
②眠ることから意識をそらす
眠ろうとすればするほとかえって眠れないものです。眠りたいという意識のそらせるのは、なかなか難しいものです。床の中で好きな音楽を聴くのも一つの方法です。また、関心のあること考えるのもよいと思います。仕事のことでも趣味のことでも、夢中で考えているうちに眠っていたということもあります。
その他自律訓練法などのやり方もありますが、自分に最も合った方法で実行してください。